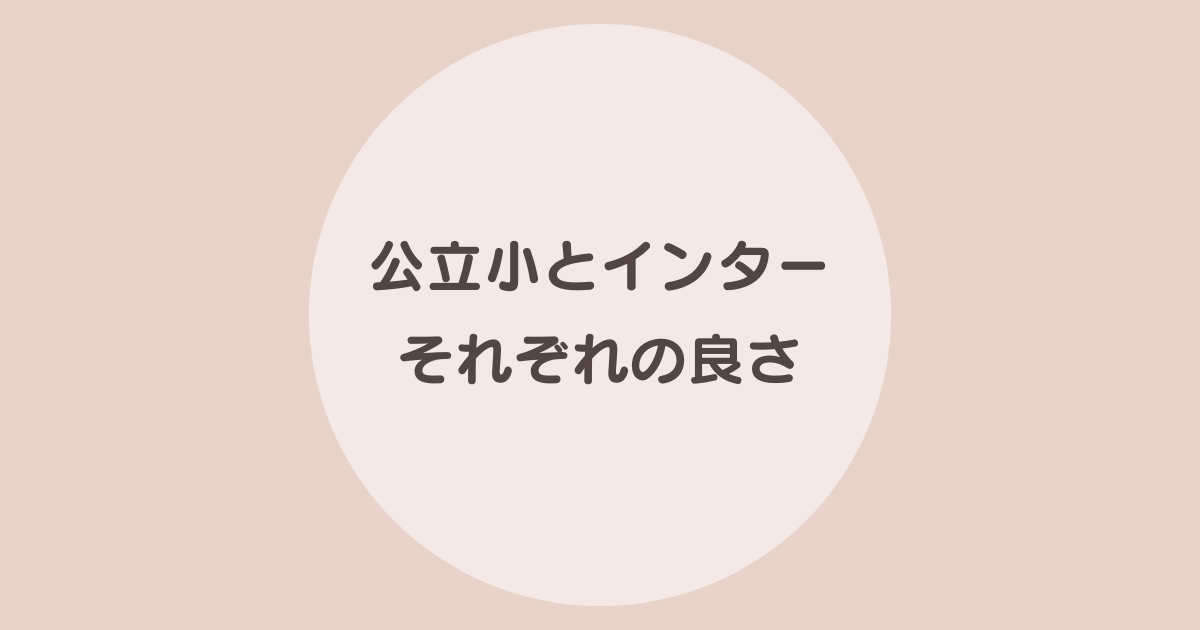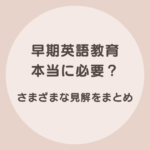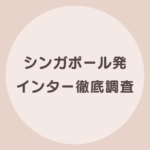昨今、子どもの英語教育に関心を持つ家庭が増えています。
公立小学校に通わせるべきか、それともインターナショナルスクールや私立の選択肢を検討すべきか、比較したい親御さんが多くいるでしょう。
「経済的にインターは難しいけれど、将来の英語力には妥協したくない」という思いを抱える方もいると思います。
一方で、日本の公立小学校でも英語教育は近年大きく進展しています。

しかし、その内容や効果に対する評価は、家庭によってさまざま。
「本当に意味あるの?」「これでバイリンガルになれるの?」という不安があったり、すでに英語に触れている子どもにとっては学校の英語が物足りなかったりします。
一律に、小学校英語が始まったことでメリットが多いとは言い切れない部分もありますよね。
この記事では、英語教育に関心のある保護者の視点から、公立小学校の教育の特徴や実際の英語教育の内容を解説します。
英語教育に興味のある親御さんが注目するインターナショナルスクールとの比較や、インターに通うのが難しい場合の家庭での英語教育もご紹介します。
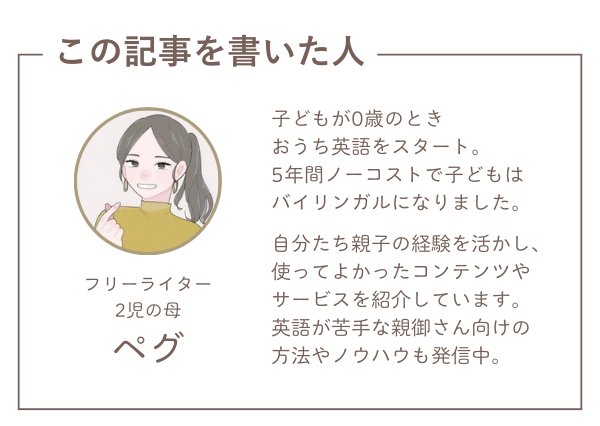
※本ページにはプロモーションが含まれています
Contents
日本の公教育における英語教育の特徴
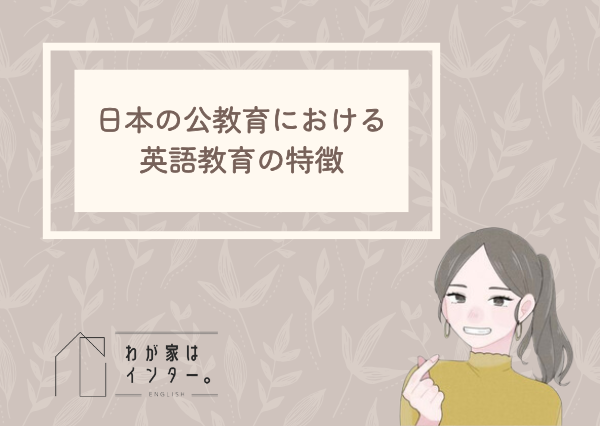
日本の公立小学校では、2020年度から英語教育が大きく変わりました。
小学3~4年生では「外国語活動」として、聞く・話すを中心としたコミュニケーション体験を行います。
5~6年生になると正式に「教科」として英語が導入され、いわゆる成績がつく"評価対象"にもなります。
授業ではALT(外国語指導助手)と担任が協力しながら、英語の活動をします。
歌・ゲーム・簡単な会話表現などを通して、英語に対する抵抗感をなくすことが目的です!
また、小学校英語の教科書には「I like〜」「What time is it?」など基本的なフレーズが繰り返し出てくる構成になっており、子どもが楽しみながら慣れていけるよう工夫されています。
一方で、教員の英語力や指導経験には差があるのも事実。
地域や学校によって、授業の質にばらつきがあるという課題も残っているようです。
教員の年齢によっても、まだ詰め込み式(単語や文法を暗記するやり方)を続けている人、コミュニケーションスタイルにシフトする人など、さまざま。

インターと公立小の英語教育の違い
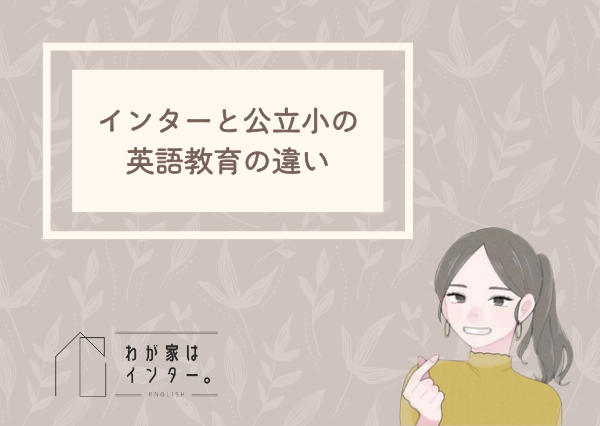
子どもの進学先としては、公立小学校のほかにインターナショナルスクールに通うという方法もありますね。
まずは、両者の違いを表で見てみましょう。
| 比較項目 | 日本の公立小学校 | インターナショナルスクール |
|---|---|---|
| 設立母体 | 公的機関 | 民間または大使館など(私立) |
| 使用言語 | 主に日本語 | 主に英語(または他の外国語) |
| 教育課程 | 日本の学習指導要領に準拠 | 各校独自のカリキュラム (IB、アメリカ式、英国式など) |
| 学費 | 基本的に無償 | 年間100〜300万円以上が |
| 対象生徒 | 日本国籍の6〜12歳の児童 | 主に外国籍児童 帰国子女、日本人も可 |
| 教員資格 | 教員免許保有の教員 | 外国人教員中心 教員資格をもたない人もいる |
| クラス構成 | 同年齢・一斉授業 | 少人数・異年齢・個別指導型 |
| 英語教育 | 小3から必修 | 英語で生活・学習をする |
| 文化・行事 | 日本の伝統・四季行事重視 | 多国籍文化のイベントが多い |
| 評価方法 | テスト・通知表中心 | パフォーマンス評価 |
英語教育において、インターナショナルスクールと公立小学校では大きな違いがあります。
まず、インターでは授業そのものが英語で行われ、英語が生活言語(母語のように使われる言語)として機能します。
これは、インターが「日本在住の外国人生徒を対象にした教育施設」だからです。

一方、公立小では英語は「教科のひとつ」であり、使用時間は週に1~2コマ程度。
日常的に英語に触れる環境ではありません。
また、インターでは国際バカロレアなどのカリキュラムに基づき、思考力や表現力を英語で伸ばす取り組みも行っていますよ。

一方、公立小には費用の面での安心感があります。
日本語による基礎学力の習得や、日本社会の文化的背景を学ぶことができるというメリットもありますね。
家庭の価値観や将来設計に応じて、どちらが子どもに合うかを見極める必要があるでしょう。
わが家ではおうち英語をしているほど英語教育に力を入れていますが、それでも「公立小学校よりインターが良い」とは言い切れない部分があります。
それは、日本の公教育がいかに良質かを、子ども2人を通わせて身に染みて感じているからです。
まずは、実際に公立小学校とインターを比べたことがある人たちの声を見てみましょう。
公立小学校とインターを比較した世間の声
それでは、実際に公立小学校とインターを比較した世間の声を見てみましょう。
インターから公立小学校に編入したご家庭やその逆など、さまざまなケースがみられます。
どちらが優れているということではなく、あくまでご家庭の教育方針によって好みが分かれるようです。
息子たちがインターから公立の小学校に移って半年ちょっとが経った。
心の底から、公立に移してよかったと思ってる。
体育、家庭科、書道、工作、給食当番、委員会活動...
本当にたくさんの家では学べないコンテンツを提供してくれる。
しかも無料で。…— 東大博士号ママ✏️こども英語と知育 (@natsumi_shibata) June 17, 2025
シンガポールのインター校で「色んな国籍の人がいて多様性がすごい」というの、それ真逆ですから。あんなに均質的な環境はない。国籍は違っても、親が会社役員や経営者の同じ階層で、シンガポール/NY/ロンドンをぐるぐるまわってる。
多様性っていうのは、シンガポールの徴兵や、日本の公立小学校です https://t.co/ztANFfbPHx— うにうに (@uniunichan) July 15, 2024
インターママ友と同級生の子が遊びに来てくれた。「インター生の悩みって、いつか日本の公立に転校するときがきたとしたら、ルー大柴みたいな話し方で浮くかもってことかな。」「カタカナ英語の発音とかね笑」でも人と違う秀でるものがあるからこそ価値がある。そこに辿り着くよね😌 pic.twitter.com/GKUokq0JNn
— ルイッピーMom@純ジャパ教育移住Fam🌏 (@louippi_chiiku) July 11, 2024
今日からキッズが公立小に体験入学。
説明受けに行ったらカリキュラムも施設も充実して最高。マジで中途半端な私立やインター行かせるなら公立が良くないか?
様々な子を見てるから安心感も桁違い。うちのキッズのゴリゴリなタメ語にも笑顔で対応してくれる器の広さ。お世話になります。— かつお@FIREx海外移住x「カナエル」開発中 (@katsuoru) June 24, 2025
上の子達が海外育ち、インター、私立小だったので。公立保育園の下の子の友達が日曜日に家にピンポンしにくるの新鮮だし可愛い。
親同士はインターや私立小の方が似たもの同士で仲良くなりやすいけど、23区だと住んでる人も似通っているから公立小・公立保育園もなんか上手くやっていけそうな気がする— ゆとり (@yutorimamalife) May 26, 2025
インターは多国籍であり、公立小は日本人や日本語を母語とする子どもが多いため、文化の違いが顕著ですね。
その文化になじめるかどうかも、インター派と公立小派に分かれる理由になっています。
次の項目でくわしい調査結果を見てみましょう。
インターから公立小への転校は8~9歳が最多
ここでは、JOIインターナショナルスクールによる調査(2024年)の結果を抜粋してみます。
子どもをインターナショナルスクールに通わせていたご家庭のうち、65.1%が途中退学していることがわかっています。
途中退学した年齢でいちばん多いのは、8~9歳で28.5%でした。

小学校6年生まで通わせていたかどうかまで範囲を広げると、なんと84.5%のご家庭が小6までにインターを辞めているそうです。
主な理由は以下の通りでした。
- 学校になじめなかった(23.5%)
- 学費が高かった(20.0%)
- 教育内容に満足できなかった(19.0%)
- サポート体制に満足できなかった(17.5%)
- 通学が不便だった(17.5%)
インターを辞めた子どもの大半が、学校になじめないという理由で転校しています。
転校先は公立小中学校がもっとも多く、36.5%であることがわかりました。
次いで私立の学校が28.0%、一条校ではないオルタナティブスクール(※1)が22.5%という結果でした。
※1…オルタナティブスクールとは、フリースクールやモンテッソーリ教育校など、従来の公立/私立校とは違うカリキュラムを持った学校のこと。
【参考サイト:JOI】
また、インターを辞めた19.0%のご家庭で「教育内容に満足できなかった」と答えていることもわかっていますね。
別の調査によると、保護者がインターに求める内容として、59.0%が「英語力向上」と回答しています。
半数以上のご家庭で、英語力向上を求めてインターに通わせていることがわかりました。
それと同時に、インターを辞めたうちの19.0%が「教育内容に満足できなかった」と回答していることから、一部の生徒はインターに通っても英語力向上が見込めなかったということが考えられますね。
公立小からインターへの転校は統計ほぼなし
インターから公立小学校への転校というケースはある程度存在し、統計もとれていますが、逆パターンはほとんどないようです。
しかし、統計がとれていないのは別の理由もあります。
インターナショナルスクールは文科省の「学校基本調査」の対象外で、国として「公式な転校先」として扱われていません。
そのため、公立小からインターへ転校するケースは報告義務がなく、単に「公教育から離脱した」とみなされるだけのようです。

しかし、それでも公立小からインターへの転校は少ないと考えられます。
まず、インターは途中入学を受け入れていない学校があります。
さきほどのJOIインタナショナルスクールの調査で、インターに通い始める年齢は5歳以下が多いと報告されていました。
インター側も低年齢からの受け入れは積極的ですが、小学校3年生くらいになると募集停止をする学年も出てきます。
言語力の差や授業の難易度など、インター側と生徒の齟齬を防ぐために、高学年になればなるほど公立小からインターへの転校はしづらくなるのです。
また、公立小から転校するというケースの場合、大半が緊急時であると思います。
引っ越しや家庭の事情(離婚など)、またいじめによって環境を変えることもあるでしょう。
そのような事情があるとき、あえて「インター」を選ぶご家庭が少ないと推測できるのも、公立小からインターへの転校ケースがあまりみられない要因ではないでしょうか。
公立小とインターはどちらが高学歴になる?
公立小学校に行かせるルートとインターに行かせるルートでは、どちらが高学歴になるのか。
進学先に迷っている親御さんの中には、気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からいうと、以下のように考えられるでしょう。
- 日本国内の名門大学への進学であれば公立小が有利
- 海外大学やグローバル系私立大への進学であればインターが有利
学歴といってもさまざまな系統やルートがあり、それは将来的にどのような職に就きたいか、また移住したい国があるかなど、ご家庭や個人の目的によっても変わってきます。
たとえば日本国内の名門大学であれば、受験対策が整っている公立小学校で日本の教育を受けるほうが有利でしょう。
教科書・入試の基準が国内共通で明確であり、受験に必要な日本語力も育ちやすい環境です。
高校・大学入試に強い塾・予備校にも通いやすく、受験のハードルがやや下がりますね。
インターの場合は受験対策というより、英語力・プレゼン力・批判的思考など世界標準のスキルが身につくのがメリットです。
そのため、インター出身の人は海外大学への進学も目指しやすいですが、近年では上智・ICU・早慶の国際学部、立命館アジア太平洋大(APU)などの受け皿も充実しています。
偏差値や名門大学を重視するご家庭なら公立小(からの中学受験など)を目指すこともありますし、多様な進路を考えたいのであればインターを出て世界に飛び立つという道もありますね。
結果、どちらが高学歴になると断定できるものではなく、ご家庭の方針や子ども本人の夢・目標によって、適した環境が異なるということでしょう。
公立小学校のメリット
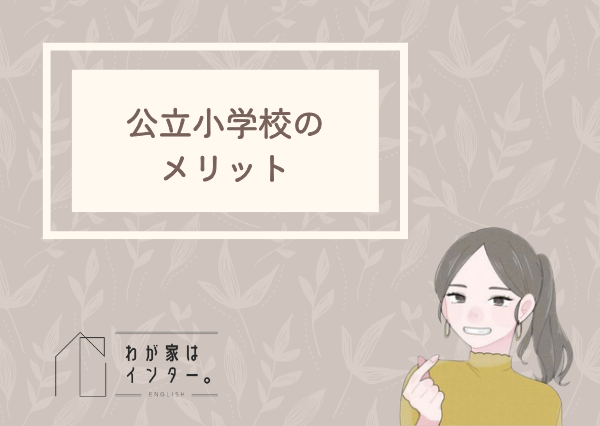
英語教育に関心のある親御さんは、どうしても次のように考えてしまいがちだと思います。
公立小よりもインターのほうが良いに決まってる!
これからの時代、古き良き日本教育よりもグローバル教育を受けるべき!
確かに公立小学校では、英語教育やダイバーシティ教育に遅れがある側面も存在しますよね。
わが家にも発達障害児がいますので、その点で生きづらさを感じることがあります。
しかし、公立小学校にはそれ以外に大きな強みがあるんです。
世界的に称賛されている日本の公教育の質や、実際にわが家で感じるメリットを解説していきましょう。
教育レベルに地域差がない
日本の公立小学校は、全国で統一された学習指導要領に基づいて運営されています。
そのため、どの地域でも安定した教育を受けられるという「均質性」が担保されているのがメリット。
読み書きや計算などの基礎学力は世界的に見ても高く、国際学力調査(PISAなど)でも日本の子どもたちは上位に位置しています!
参考:ベネッセ
日本の公立小学校では、使用する教材や授業内容、学習進度などにおいて地域による差が少ないという特徴があります。
これにより、たとえば転校をしても学習内容に大きなズレがないため、子どもが安心して学びを継続できるというメリットがあるのですね。
また、教員採用試験も都道府県ごとに行われ、一定の基準を満たした教員が配置されます。
地域や学校によって、教育の質が大きく崩れることは少ないといわれていますよ。
それでは、海外諸国の公教育を例に挙げてみましょう。
例1:アメリカ
- 州や学区によって教育方針やカリキュラム、予算の配分が異なる
- 学区の財政力が学校の教育環境の質を左右する
- 同じ公立小学校でも、地域によって教育格差がある
アメリカは上記の特徴があるため、裕福な地区の学区では、最新の設備と優秀な教員、豊富な課外活動が整備されています。
一方、経済的に厳しい地域の学区では、老朽化した校舎や慢性的な教員不足、教材やICT環境の不足などが顕著化しているのです。
そのため、多くの親が「良い教育を受けるには良い学区へ引っ越さなければいけない」と考え、優秀な学校に生徒が集まる傾向にあるそう。
そして、経済的に厳しい地域の学区には生徒が集まらず、教育の質が上がらないまま…という問題が深刻化しているのです。
また、高額な授業料を支払って私立校やチャータースクール(※2)への進学を選ぶ家庭もあります。
※2…保護者や教員、地域が州や学区の認可を受けて設立する、公費で運営される学校のこと
例2:ドイツ
- 10歳前後で能力や進路に応じて進学先が分かれる
- 移民や社会的背景による学力格差が生じている
- 日本のような集団教育の期間が短い
ドイツでは上記の特徴があり、日本とは大きく違う教育スタイルであることがわかります。
小学校では日本と比較的類似した教育が行われますが、10歳前後で個々の能力や家庭の進路方針に応じて「分岐」するのが特徴。
大学進学を前提とした教育か、職業訓練重視の学校のどちらかに振り分けられ、早い段階で教育が個別化します。

例3:フィンランド
- 教員は修士号取得が必須という高い専門性がある
- 生徒一人ひとりに合ったサポートを行う「特別支援教育」がさかんである
- 宿題やテストが少なく学習意欲を育てることを重視
フィンランドは日本と似ていて、公立小学校であればどこでも均一の教育を受けることができます。
さらに教員のレベルが高く、発達障害や学習障害を持つ子どもに適した「特別支援教育」にも力を入れている点は、日本と異なる部分ですね。
集団生活のルールを学べる
日本の公立小学校は、規律や集団生活のルールを重視した教育が行われます。
日本社会の中で生活するうえで重要な土台となる以下の習慣を、公教育で身につけることが期待できるのがメリットでしょう。
- 時間を守る
- 挨拶をする
- 掃除をする
- 配膳をする
上記の習慣や能力は将来、どのような進路を選ぶにしても、子どもの生きる力を支えてくれる重要な資質になりますね。
では、この部分を海外諸国の教育と比較してみましょう。
| 国・地域 | 教育観 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 日本 | 集団主義・規律重視 | 調和・空気を読む・当番活動 |
| 韓国 | 競争+集団行動 | 厳格な校則・塾文化・偏差値社会 |
| 中国 | 上下関係+集団 | 礼儀重視・管理型教育 |
| フィンランド | 個性・自律重視 | 宿題なし・テスト少なめ・自由時間 |
| オランダ | 自己表現・主体性 | ディスカッション中心・机の自由配置 |
| アメリカ | 個人主義・自由重視 | 州・学校によって差・ESL対応あり |
中には、日本と似て集団行動や上下関係の大切さを説く、教育的特徴のある国もあります。
まずは日本と共通した教育が施される、アジア圏の国について見てみましょう。
例1:韓国
- 集団活動・制服・整列・一斉授業が主流である
- 礼儀や年齢による上下関係が厳しい
- 学習塾文化や受験重視が強い
隣国・韓国では、日本と似た教育観が顕著です。
上下関係や年齢による礼儀作法は日本よりも厳しく、子どもが親に敬語を使う文化もあります。
日本も韓国も礼儀作法が厳しい傾向にありますが、日本では明治時代あたりから西洋の文化を取り入れるようになってきたため、韓国よりは緩くなってきたそう。

また、韓国は日本以上に受験戦争が激しく、家族ぐるみで子どもの受験をバックアップします。
そのため、学校教育も受験に合わせたカリキュラムになっていることが多く、厳格で偏差値重視の教育がメジャーなのですね。
例2:中国
- 学年やクラスでの上下関係・集団主義を教えられる
- 礼儀や先生への敬意が強調される
- 管理型の授業スタイルが主流である
中国でも、日本と同じようにクラスや学年での上下関係や、礼儀作法について教えられます。
しかし、日本や韓国に比べるとフランクな文化であることも特徴的で、一部の学校では欧米型のアクティブラーニングが導入されているそう。


中国の孔子に始まった「儒教」という思想が、東アジアの文化や教育の基盤になっているという説が有力です。
儒教の教えと日本、そして韓国や中国での教育観に共通しているのは、以下のような考え方でしょう。
- 年長者・教師・親を敬う
- 礼儀・秩序を守る
- 個より集団・秩序を重んじる
- 知識より徳を重視する
このような儒教の教えにより、わたしたちは「教師の指示に従う」「みんなと同じ行動を取る」という教育がなされていますよね。
また、東アジアは農耕社会の文化があり、稲作には村単位の協力や一致団結が不可欠。
そこから、集団での調和と協力が重視される文化や教育が始まったともいわれています。
生活指導・道徳教育が充実している
日本の公立小学校では、世界的にも絶賛されている教育的文化があります。
それは、給食当番や掃除当番など、学校生活を基盤とした生活指導、道徳教育が充実していることです。
日本の公立小学校では、掃除や配膳を外注せず自分たちで行う独自スタイルの教育がありますよね。
わたしたちは当然のように給食当番をしたり、掃除当番では下級生に掃除の仕方を教えたりしてきました。
しかし、世界的に見ると非常に珍しい教育観なのだそうですよ。
国際番組やBBCなどでたびたび紹介され「驚くべき教育モデル」として評価されることもあります。

ベトナムやタイでは、日本の教育スタイルを模倣する試みが行われているとか!
欧米では配膳や掃除を子どもたちがすることは基本的になく、学校職員の責任と考えられています。
ケガやミスを防ぐためにも、配膳や掃除は教員が行ったり外注したりするべきという"人権的な考え方"があるのだそうです。

長期的に見て大きな力を育てる日本の生活指導力は、世界的に見ても独特で、また高く評価されているのですね。
また、日本の公立小学校では栄養満点の給食が出るのも、特徴の1つです。
Youtubeや海外ドラマを見るとわかると思いますが、欧米では基本的に給食がありません。
「食育は家庭の責任」という考え方が強いからだそうです。
教育現場では学問的な責任だけを負い、日本のように「食育」まで提供できる経済的余裕がない学校もあるのだとか。

インターのメリット
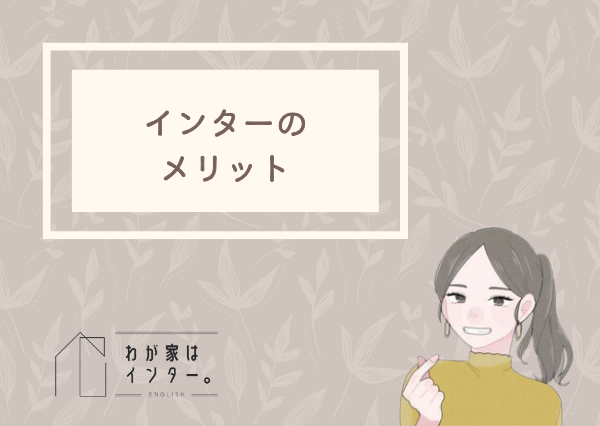
では、インターナショナルスクールのメリットを挙げてみましょう。
まず、そもそもインターナショナルスクールは日本人向けの学校ではないということを、頭に入れておきましょう。
「インターナショナルスクール=英語を学べる学校」だと認識されていることがあるのですが、厳密にいうと違います。
インターナショナルスクールは、日本に住む外国籍の子どもたちが、いつか祖国に帰ったときにカルチャーショックを受けないよう、英語圏を中心としたインターナショナルな教育を受けられる学校です。

そのため、インターナショナルスクールに通うということは、日本の文科省のカリキュラムとは異なる独自の教育課程を辿ることになります。
しかし、昨今では「日本型インター」と呼ばれる、日本人の生徒が半数を占めるインターナショナルスクールも増えてきているそうです。
日本型インターでは、一部で日本語の授業が行われたり、通常のインターナショナルスクールと同様の国際資格を取得できたりする特徴も。

では、インターナショナルスクールのメリットを見てみましょう。
イマージョン教育が受けられる
インターナショナルスクールの最大の特徴は、英語による完全なイマージョン教育です。
イマージョン教育とは、カナダ・ケベック州で1960年代に誕生したバイリンガル教育法で、基本科目を第2言語で教えることでバイリンガルを育てるというやり方です。
イマージョン(immersion)には「浸す」という意味があり、第2言語に浸してバイリンガル教育をするというもの。
【参考:Go School】
日常会話だけでなく、算数や理科、社会などの教科もすべて英語で学ぶため、実践的な語学力が自然に身につきます。
英語を教科として学ぶのではなく、英語で学ぶ環境が整っています。
英語を「勉強」と認識する前に日常会話を通して身につけることができ、幼少期から学ぶ知識や経験のすべてを英語で得られるのは、大きなメリットですね。
将来的に、海外大学に進学したりグローバルな職業に就いたりする際に、大きなアドバンテージになるとされていますよ。
\ イマージョン教育ならNovakidでお手軽に /
-

-
【レビュー】Novakid(ノバキッド)のレベルやレッスン内容
オンライン英会話のNovakid(ノバキッド)を実際に体験したレビューをまとめています。 第1回目の本記事では、次の内容について記載しています。 この記事のまとめ ...
続きを見る
多様性と国際感覚が育つ
インターナショナルスクールには、日本人以外の生徒や多国籍の教師が在籍しています。
文化・宗教・言語の違いを自然に受け入れる環境の中で育つため、国際感覚や異文化に対する理解力が、早くから養われるのがメリットでしょう。
グローバル社会で求められる「多様性への寛容さ」や「柔軟なコミュニケーション力」が自然と身につく点は、公立小学校にはない大きな魅力ですね。
肌の色や髪の色が違う友達に囲まれて育つことは、日本の教育ではなかなか身につきにくい「みんな違って、みんないい」という感覚が育ちやすいでしょう。
-
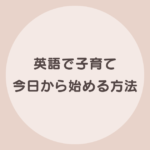
-
英語で子育てするメリットは?わが子が3ヶ月で話し始めた方法を伝授!
子どもに英語を身につけてほしい親御さんは、英語で子育てをしてみませんか? 英語で子育てをすることで、幼児期から英語に慣れ親しめるメリットがあります。 おうち英語ママでも、英語で子育てをするなんてハードルが高い! ...
続きを見る
自主性・創造性を重視する
日本の公教育では、集団行動や規律を重視する傾向が強い傾向があります。
一方インターナショナルスクールでは、主体性や個性を伸ばす教育が重視されることが多くあります。
カリキュラムの内容としては、プレゼンテーションやディスカッション、探究型学習などが取り入れられていますよ。
テーマとしては「自分の意見を持ち、発信する力」を育てる場が多くあり、この点を評価するご家庭からは、インターナショナルスクールのほうがポイントが高い傾向にありますね。

インターナショナルスクールでは、リーダーシップや起業家精神を求める人材に育てる教育環境が整っています。
日本の教育では「優等生」が育ち、インターでは「エリート」が育つというふうにいわれています!
-
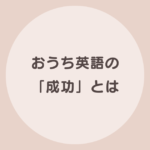
-
おうち英語の成功とは?1日30分でOK!本物の英語力をつけるコツ
突然ですが、おうち英語の成功って何だと思いますか? ペラペラになること、英検を取得すること、テストで良い点数を取ること… おうち英語の成功は、家庭によってさまざまですよね。 ...
続きを見る
学力偏重ではない総合評価
インターナショナルスクールは、日本の公教育と比べて成績や学力テストの点数だけで評価されない点も特徴です。
たとえばIB(国際バカロレア)のカリキュラムでは、思考力・探究心・協働性・倫理観が総合的に評価されます。
そのため、筆記試験が苦手な子どもや、独自の才能を持つ子どもも輝きやすく、学びのモチベーションを維持しやすい環境が整っているのですね。
日本の公教育も、昔と比べると多様性が開かれてきているものの、まだまだ筆記テストで成績が決まったり、進学もテスト結果に左右される傾向があります。
勉強ができるかどうかではなく、子どもの個性や総合的な能力を評価してほしいご家庭にとっても、インターナショナルスクールは魅力的に映るでしょう。
グローバルキャリアへの道が開かれる
インターナショナルスクールの卒業生は、以下のような進学先を選ぶ傾向があるそうです。
- 海外の大学へ進学する
- 英語で授業が行われる日本の大学へ進学する
- 海外の大学の日本校へ進学する
- 日本の一般的な私立大学へ進学する
海外の大学や、英語で授業が行われる大学に進学することは容易ではありません。
インターナショナルスクールを卒業しているからこそ、英語力の土台だけでなく、英語で学ぶ力や主体性、創造性など、海外で通用する能力が身につくのですね。
インターナショナルスクールには、上記のような進学のための情報やサポート体制も整っています。
IBやAレベルといった国際的なカリキュラムを履修すれば、世界中の大学への出願資格を得られるというメリットも。
将来的に日本以外で学びたい、働きたいという選択肢が自然に広がるのですね。
公立小学校に通いながら英語教育をするには
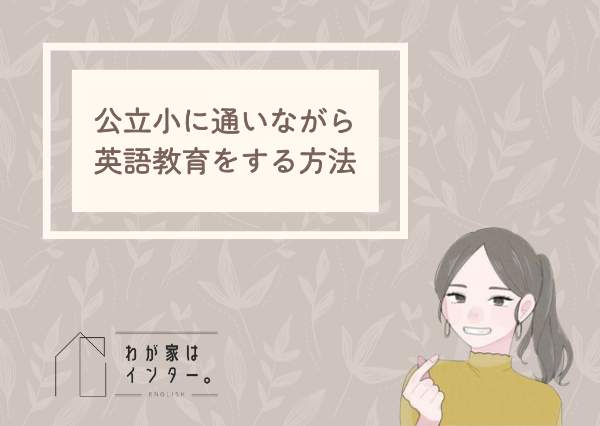
公立小学校に通うと、学校で受けられる英語教育の時間は小学校3年生から週に1~2コマ程度。
英語力がアップしたり、流暢に話せるようになるレベルには程遠い量です。
しかし、だからといって英語教育を諦める必要はありません。

おうち英語は、親御さんが子どもに英語を教えるものだと思われる方がいるかもしれません。
しかし実際には、親御さんが先生になるのではなく、幼少期から日常生活に英語を取り入れる習慣をつけるというもの。
ネイティブレベルを目指して本格的に英語環境を整えるも良し、学校教育を補うかたちで家庭でできることをするも良し。
おうち英語は、お金をかける部分も自由に調整でき、ご家庭の生活スタイルに合わせて柔軟に方法を変えられる、自由な英語教育の1つなんです。
ここからは、公立小学校に通っていてもできる英語教育をご紹介していきます。
関心のあるボックスをタップすると、くわしく解説した記事やおすすめサービスにジャンプできます。
日常的に英語の絵本を読み聞かせたり、英語の歌やアニメを一緒に観たりする「おうち英語」は、楽しく英語コミュニケーションを学べるだけでなく、小学校英語の内容と自然につながります。
また、フォニックス教材を使って発音のルールを楽しく学ぶのも、幼児期ならではの楽しみ方でしょう。
最近では、オンライン英会話や英語学童、英語絵本の読み放題アプリなども充実しています。
そのため、コストを抑えつつ継続的なインプット・アウトプットの場をつくることも可能になってきましたね。
大切なのは、学校でやっていること+家庭でできることのバランスを取りながら、子どもが英語を「楽しい」と感じる時間を積み重ねていくこと。
子どもにとって家庭はリラックスできる場所なので、安心して英語を学べて、自然に英語が染みつきやすい環境でもあります。
公立小学校の英語教育を受けながらおうち英語を並行することは、英語の知識がつくだけでなくコミュニケーション力や国際的な感覚を身につけるという点でも、効果を感じるでしょう。
まとめ:英語教育と公教育のバランスが大事
日本の公立小学校は、英語教育の面ではまだ発展途上かもしれません。
しかし基礎学力や社会性、学習習慣の土台づくりにおいては、優れた教育環境だといわれています。
インターとの比較では、英語環境の密度では劣るものの、日本語による思考力・表現力をしっかり育めるのは大きな利点となるでしょう。
「英語育児を続けたいけれど、インターには通えない」
そんなご家庭でも、公教育を受けながら英語教育を続けることは可能で、バランスのとれた英語力を育てることもできます。
家庭の価値観と現実的な選択肢のなかで、何が子どもに合うかを見極めていきましょう。
英語教育に熱心な家庭こそ、日本の公教育をうまく活かしながら、自分たちならではの学びのスタイルを築いていくことができるでしょう!
あわせて読みたい
-
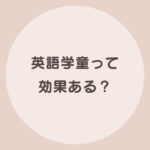
-
英語学童って効果ある?おうち英語っ子のリアル体験談まとめ
子どもの英語教育をする際「英語学童」を選択肢に入れるご家庭があると思います。 この記事では、英語学童の効果や体験談についてリアルなレビューをお伝えします。 英語学童とは、名前の通り英語を教えてくれる学童のことで、放課後の時間を有意義に過ごす方法の1つ。 ...
続きを見る
-
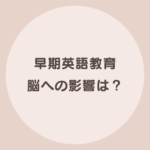
-
早期英語教育の脳への影響は?日本語が遅れる疑惑や効果の高い方法
「早期英語教育って脳に影響あるのかな?」と思っていませんか? 早期英語教育には賛否両論あり、日本語の発達に影響があったり、日本語と英語で混乱したりするリスクも懸念されています。 この記事では、科学的な研究結果や脳の発達についての権威性ある情報から、早期英語教育による脳への影響を解説します。 ...
続きを見る
-

-
今すぐできるおうち英語×モンテッソーリ|英語も知育も自宅で楽しく!
英語学習で苦労された親御さんであればあるほど、子どもには楽しく英語に触れてほしいと思いますよね。 この記事では、おうち英語とモンテッソーリ教育を組み合わせた知育・英語教育の環境づくりについて解説します。 昨今話題性を高めている英語教育と、長い歴史を持ち信頼性の高いモンテッソーリ教育。 ...
続きを見る
ブログランキングに参加しています!
応援よろしくお願いします✨